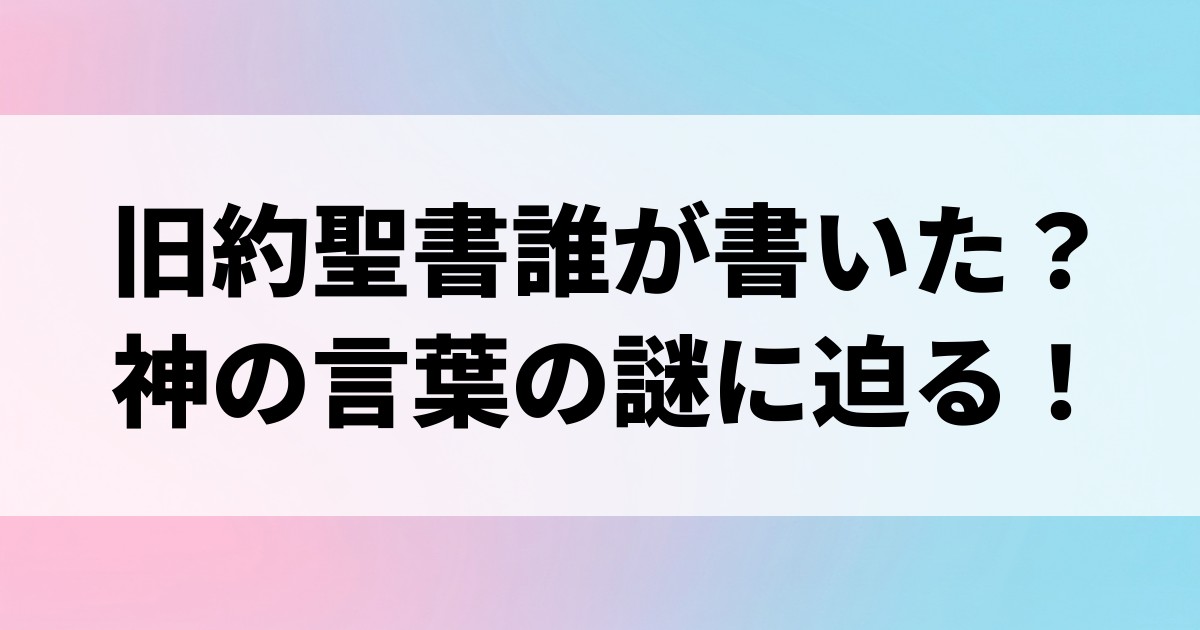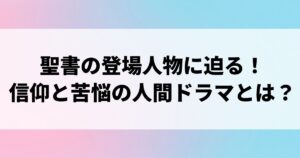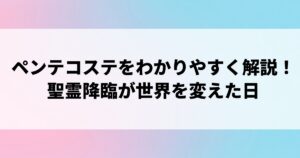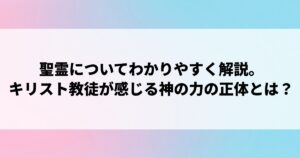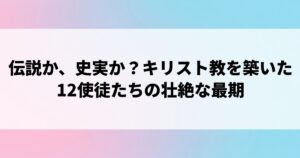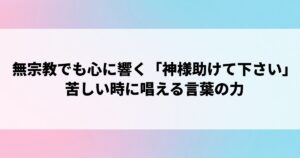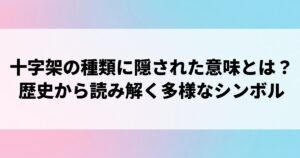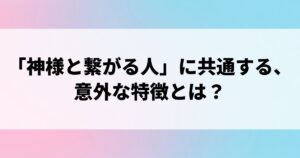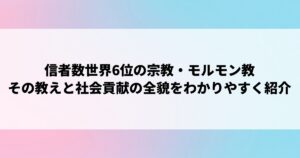旧約聖書は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典であり、人類の歴史に最も大きな影響を与えてきた書物の一つです。その内容は、世界の創造から古代イスラエルの歴史、律法、預言、詩歌に至るまで多岐にわたります。しかし、これほどまでに重要な書物が、一体誰によって、いつ、どのようにして書かれたのかについては、長年にわたって議論されてきました。本稿では、旧約聖書の著者と成立時期について、伝統的な見解から現代の学術的な見解まで、多角的に解説します。
旧約聖書は誰が書いたのか?
旧約聖書の基本構成と全体像
旧約聖書は大きく分けて、律法(トーラー)、預言書、諸書(ヘブライ語聖書では「ケトゥビーム」)の3つに分類されます。律法は「モーセ五書」とも呼ばれ、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記から構成されます。預言書には、イザヤ書やエレミヤ書などの主要な預言者の書と、12の小預言者の書が含まれます。諸書は、詩篇、箴言、ヨブ記などの文学作品や、ルツ記、エステル記、歴代誌などの歴史書で構成されています。
モーセ五書の著者と伝承される背景
旧約聖書の中でも特に重要なモーセ五書は、伝統的に預言者モーセが一貫して執筆したと考えられてきました。出エジプト記や申命記には、モーセが神からの言葉を書き記すように命じられた、またはモーセが自ら律法を書き記したという記述が複数箇所に存在します。例えば、申命記の「この律法の言葉を、一冊の書物に書いて完成した」という記述がその根拠とされてきました。しかし、モーセの死とその後の出来事が記述されている部分もあるため、モーセ単独の著者説には疑問が呈されるようになりました。
預言書・詩篇・歴史書などの著者の特定と議論
モーセ五書以外の書物についても、著者の特定には多くの議論があります。預言書は、イザヤ書であれば預言者イザヤ、エレミヤ書であれば預言者エレミヤというように、その名がタイトルに冠されている人物が著者であると考えられています。しかし、書物の内容を詳細に分析すると、一人の人物が執筆したとは考えにくい部分も見つかります。例えば、イザヤ書にはバビロン捕囚以前と以後の異なる時代背景を持つ記述が含まれており、複数の人物による執筆や編集の可能性が指摘されています。
詩篇は、その多くがダビデ王によって書かれたと伝えられていますが、ソロモン王やモーセ、さらには無名の著者によるものも含まれています。諸書に分類される歴史書は、複数の資料や口伝を編纂したものであり、特定の個人による執筆ではないと考えられています。
旧約聖書の成立時期
口伝から文書化への移行過程
旧約聖書に記述されている物語や律法は、最初は口頭で世代から世代へと伝えられていたと考えられています。古代社会では文字が限られた人々にしか使われていなかったため、歴史や信仰の伝承は口頭での語り継ぎが中心でした。物語や詩歌は、共同体の記憶として口伝によって共有され、特に宗教的な祭りや儀式の場で繰り返し語られることで、その内容が人々の間に深く浸透していきました。こうした口伝は、単に事実を伝えるだけでなく、共同体のアイデンティティや価値観を形成する上で重要な役割を果たしました。やがて、より多くの人々に信仰を広め、またその内容を正確に後世に伝えるために、文書として記録されるようになりました。この文書化の過程は非常に長い期間にわたって進行し、複数の編者や改訂者が関与したと考えられています。
複数の編者による加筆・修正の可能性
現代の聖書学では、旧約聖書は一人の著者によって書かれたのではなく、複数の著者や編者によって、時代を超えて加筆・修正されてきたという見解が主流です。特にモーセ五書については、後に詳述する「文書仮説」が広く受け入れられています。この見解によれば、異なる時代や地域で成立した複数の文書が、最終的に現在の形に編集されたとされています。この複雑な編集過程は、聖書の内容に重複や矛盾が見られる理由の一つとも考えられています。例えば、創世記の天地創造の物語には、神の呼び名が「エロヒム」と「ヤハウェ」で使い分けられている部分があり、これは異なる二つの伝承が統合された結果と解釈されています。こうした加筆・修正は、単なる編集作業に留まらず、それぞれの時代の神学的な解釈や歴史的な背景が反映された結果と考えられています。
バビロン捕囚と聖書編集の関係性
旧約聖書の成立において、紀元前6世紀のバビロン捕囚は極めて重要な出来事でした。紀元前586年、新バビロニア帝国によってエルサレム神殿が破壊され、多くのユダヤ人が故郷を追われ、バビロンに強制的に移住させられました。民族のアイデンティティと信仰の象徴であった神殿を失い、異国での生活を強いられた彼らは、信仰の存続と民族の歴史の再構築に迫られました。この危機的な状況下で、彼らは口伝や断片的な文書として存在していた聖典を組織的に収集・編集し、後世に伝えることの重要性を強く認識したと考えられています。この時期に、現在の旧約聖書の骨格が形成され、律法や預言が体系的にまとめられたとする説は多くの学者によって支持されています。バビロン捕囚は、単なる歴史的な出来事ではなく、旧約聖書の成立という側面から見ると、ユダヤ民族の信仰が危機を乗り越えて再構築されたプロセスでもあったのです。
旧約聖書の著者に関する学術的視点
文書仮説(JEDP説)とは何か
現代の聖書学で最も広く知られているのが「文書仮説(JEDP説)」です。この仮説は、モーセ五書が複数の異なる文書資料(J資料、E資料、D資料、P資料)を統合して作られたと主張するものです。
- J資料(ヤハウィスト): ヤハウェという神の名を使用し、神を擬人化して描写する紀元前10世紀の南ユダ王国で成立したとされる資料。
- E資料(エロヒスト): エロヒムという神の名を使用し、預言者や夢による啓示を強調する紀元前9世紀の北イスラエル王国で成立したとされる資料。
- D資料(申命記史家): 申命記を中心に、律法を遵守することの重要性を説く紀元前7世紀の資料。
- P資料(祭司資料): 律法や祭儀の規定に焦点を当て、秩序と体系を重視するバビロン捕囚後の祭司集団によって編集されたとされる資料。
これらの資料は、それぞれの時代やコミュニティの思想を反映しており、それらが組み合わされることで、旧約聖書が重層的で豊かな内容を持つようになったと説明されます。
考古学や言語学による著者推定の試み
聖書の著者や成立時期を特定するために、考古学や言語学も重要な役割を果たしています。死海文書のような古代の写本の発見は、聖書の本文がどのように伝承されてきたかを知る上で貴重な情報を提供しました。また、言語学的な分析によって、書物内の語彙や文法の違いから、異なる時代や地域の著者の存在が示唆されています。
ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の解釈の違い
旧約聖書は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という3つの主要な一神教にとっての聖典ですが、それぞれの宗教でその解釈には違いが見られます。ユダヤ教では、旧約聖書(タナハ)は神がモーセを通してイスラエルの民に与えた律法であり、神の永遠の言葉として尊重されます。キリスト教では、旧約聖書はイエス・キリストの到来を預言するものであり、新約聖書と合わせて一つの救済の物語を形成すると解釈されます。イスラム教では、ムハンマド以前の預言者たちが受けた啓示の一部として、モーセの律法や詩篇が認められていますが、聖書が人々の手によって改変されたと考えられています。
まとめ
旧約聖書は、単一の著者によって書かれた単一の書物ではなく、複数の著者と編者によって、数世紀にわたる複雑な過程を経て成立した書物であると考えるのが妥当です。この多層的な成立過程こそが、旧約聖書に深みと多様な解釈を与え、今日まで多くの人々に読み継がれる理由の一つかもしれません。旧約聖書は、古代の人々の信仰、歴史、文化の結晶であり、その謎めいた成立背景を知ることは、より深くこの書物を理解する上で不可欠な視点となるでしょう。